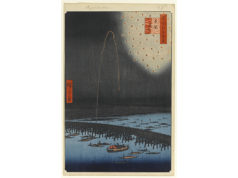2016年元旦の東京は晴天、外は静かである。年の始めにあたり日本という国はどうあるべきか、人々はそう自問しまた問いかけていることがメディアを通してわかる。昨年が終戦から70年目という節目の年ということもあり、この問いは暮れから聞かれていた。新聞(「東京新聞」)に毎日掲載される「読者の声」などによると、「戦争のできる国になってほしくない」という答えが多い。今日の朝刊に二面を割いた「新春対談」も同じような内容だった。
こういうことの裏には、昨年安倍内閣によって強硬採決された「安全保障関連法」(この3月から実施される)や「秘密保護法」がある。長年米国に住んでいるわたしの感じ方からすると、その法の運用を誤らないよう見張るのは選挙民の仕事で、国家にとってそういう法律はあたりまえ。しかし大方の日本人は、そういう法律があるだけで危機を感じているようで、その発効がすなわち「戦争のできる国」への突入の危険と考えるらしい。
「わたし( たち)は大変な思いをした。もう二度と……」――。これが先の大戦(とくに対米戦)を言うときの語り口だが、それを語り、また分かちあうことが反戦運動の一翼になると信じている人は多い。それもいいだろう。しかし反面、専門の歴史家を除き、まったく聞かれないのは、「なぜ日本は戦争を始めたか、避けることはできなかったのか」という根源的な問いだ。その結果、「あの戦争に引きずり込んだのは軍、個々の軍人というよりは軍の組織だ」という結論に到達する。それはつまり、「国民は被害者」だったということになる。戦争責任について決して忘れまいとしているようなドイツ人(および彼らが選んだ政府)との差がここにあるのではないか。
ドイツが今も自己責任を追及してやまない(ように見える)のは、ヒトラーの台頭を許したのは選挙民自身だ、と考えるからではないか。たしかに、日本人はユダヤ人抹殺などの暴挙には到らなかった(共産主義者の弾圧行為などはかなり激しく、犠牲者も多かったのだが)。そこで、ヒトラーにあたる指導者に国民が従うようなことは日本には起こらなかった、とそれで済ましているのではないか。
そして、これが決定的な点かもしれないが、広島と長崎への原子爆弾投下が日本をドイツの場合とは異なるものにしている。原爆投下が日本人のすべてを被害者意識に陥らせているから、国民一人ひとりは軍の犠牲者、戦争の責任はないと思うのではないか。
片や戦争責任の検証の有無、もう一方の「戦争のできる国
にはしない」という今の日本人の思いの2つには、どのような関係があるのだろう。それが知りたいが、新聞紙上などで論じられるオピニオンリーダーたちのあいだでは素通りのようだ。先の戦争を引き起こし加担したという歴史の事実と国民ひとりひとりの責任の間には何もない。後代に伝える必要はないということか。例外は戦死した友人戦友を持つ、年々少なく年代の男たち。何十年も昔の出来事だから関係ないという意見はどこの国にもあるものだが。
米国との連携強化によって将来の危機に備える、という安倍内閣が昨年立法した安保立法や秘密保護法に反対する。そしてそれが「戦争のできる国にはしない」という決意を生む。というわけで、こういう声には反米の感じがつきまとう。今の日本人一般の間にある「米国の文化文明は好きだが政治は嫌い」となるわけだ。まあ、当然だろうが。
その一方、原子爆弾の被害者であるにもかかわらず福島の大災害が引き起こされた。そして今、たった5年しかたっていないのになぜ原子炉の使用が再開されたのだろうか。もっといえば、なぜ民主主義の論理で運営されるはずの政府決議を止めることができないのか。これが日本人が今直面しなければならない課題だろう。その点、SEALDs ( 自由と民主主義のための学生緊急行動、シールズ)のような高校生も含めた若い層の間に広がりつつあるのは心強い。彼らが「戦争をしない日本」や「憲法護持」ではなく、「民主主義とは何か」に焦点を当てているからで、わたしには納得がいく。
(田中 幸子)