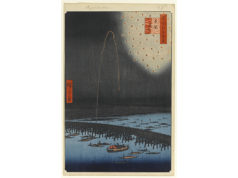外国からの観光客が多く訪れるということでメデイアで取上げられるのが、新宿にある「ゴールデン街」だ。歌舞伎町からほど近い。1960年代から70年代にかけては、作家や芸術家などの文化人が出入りする場所であり、「いちげん」客は入りにくかったものだという。
ゴールデン街の前身は、いわゆる「青線地区」だ。1958年に成立した売春禁止法で廃業を強いられた娼婦たちが「自営」という苦肉の策に商売を出した場所である。狭く貧相な店舗が長屋のように横並びに続く。階下では酒を出し、二階ではその後の商売をやった。その頃は、700円で一晩過ごせたうえ、朝食まで食べさせてくれたと証言する人もいる、とどこかで読んだ。
「青線]や「赤線」地区だった場所が、飲み屋街にかわることはよくある。長く日本に在住し、「居酒屋文化」について著書のあるマイク=モラスキー氏によると、「赤線地区は派手な色の看板をかかげる「スナック」街になり(吉原があった辺りへ行くとわかる)、青線の引かれた場所は間口の狭い二階建ての小料理屋やバーが集まる街になることが多かった」という。
現在も、ゴールデン街には、せいぜい20フィート平方の狭いバーがいくつも並んでいる。現在の店舗にも、ずいぶんと昔から営業しているものもある。昔ながらの常連に言わせれば、かつてのゴールデン街は、「誰でも受け入れる用意のある」場所で、居心地のいい場所だったという。外国人観光客の間でこのゴールデン街が人気スポットになっているのは、ゴールデン街の昔からの伝統を引きついでいるからなのかもしれない。
新宿駅の西口側から東口方面へと出る途中にある「思いで横丁」も、外国人観光客のあいだに人気があるそうだ。こちらは戦後すぐにできた闇市の跡なのだが、お世辞にもきれいとはいえない。しごく狭いスペースでの営業だ。親しみやすさと値段の安さが人気で、もちろん日本人客も多い。彼らは思い出横丁に、その名のように、なつかしさを感じるのだろう。「昭和の雰囲気」である。それに対し、外国人観光客は「こんな所は自分の国にはない」とめずらしがるのだろうか。いや、香港や台北などのアジアの都市には似たような所があるわけだから、そちらから来た観光客は安心感を覚えるのだろうか。多少の胡散臭さがあるものの、ここは日本だから安全だと思うのか。
ゴールデン街や思い出横丁の特徴は、まずそこが狭い空間であることだ。客はそこで見知らぬ他人と肩をよせあい、ひとときを過ごすことができ、それが人間にとって基本的な食べるという行為とむすびつく。そこにあるバーや食べ物屋は、日本中どこにでもある「居酒屋」と基本的にはかわらない。「居酒屋」とはなにか、その文化についてはモラスキー氏の本を読めばいい。彼に言わせれば、「居酒屋」は現代日本人の精神安定に必須な場であるそうだから、その効果を外国からの客も感じとっているのかもしれない。
『ブレードランナー』(1982年)という、世界の終焉がテーマのサイエンスフィクション映画があった。始まりのシーンにアジア的な雰囲気の屋台街のような場所があった。あたりにはネオンが点滅し、遠方には超近代的なビルの頭が見える。日本語の看板らしきものもあったと記憶する。思いで横丁を思わせる一角で、人々はもくもくと何かを食べていた。ゴールデン街や思い出横丁に共通の特徴は、「狭い空間」で、あかの他人がいっしょに飲み、食べる。そこが、私の中で、ブレードランナー的世界と重なるのである。
東京では、近代化の名のもとに、木造の建物が壊され(地震や火事もあることだし)、鉄筋の高層ビルが建てられ(狭い国土だから)、「ニュータウン」と呼ばれる出来上がった街と駅の延長である商業ビルが、そこいらじゅうでつくられた。そういう現実に疎外感や喪失感を感ずる人々もいて、外国からの客も同じように感じとったとしても不思議はない。ゴールデン街や思いで横丁は、昔からの木造建築、みすぼらしいが謙虚な姿(なにしろ狭い)を時代の動きに逆らって保っている。そうした事実への共感がある、といったら言い過ぎだろうか。
歌舞伎町には新しいものもある。外国資本のホテルをはじめ、新しいものもたくさんある。体を横たえるだけのスペースが提供される「カプセル」ホテルもしかり。その利用者の3割は外国人とのこと。かと思うと、近くの「レストランシアター」では大がかりで派手な巨大ロボットのショーなどが外国人観光客の注目を集める。信じられないような現象が歌舞伎町に出現しているようだが、どういうことなのだろう。理由はあるのだろうが、それが何かを突き止めるのは、観光立国を経済政策の一つと決めた日本の役所の課題かもしれない。
(田中幸子)