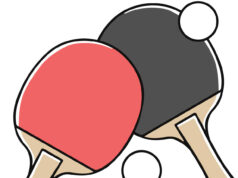「お帰りなさい、イチロー選手」。まずはこれを言わずにはいられない。マリナーズのユニフォームを身に着けたイチロー選手を、再び見ることができるとは。美しいシアトルの夏とベースボールとイチロー選手。懐かしい夏の光景が帰ってきた。
いつも4月が来ると、4月生まれの人はラッキーだなと思う。誕生石がダイヤモンドなのだ。11月生まれの私は、何とかトパーズを好きになろうとしたが、やっぱり駄目だ。そもそも誕生石が一般的に認識されるようになったのは1950年代以降。米国の宝石商会が、マーケティングを意識して誕生石リストを広めたのがきっかけだ。11月の誕生石を、こじ付け的にトパーズにしたマーケティングセンスを恨む。
それにしても、ダイヤモンドが年の始まりの1月ではなくて4月というのも疑問が残る。やっぱり4月生まれの人はラッキーだ。前にも何度か書いたが、ダイヤモンドがこんなに人を魅了することになったのは、産業革命による宝石の研磨技術の発達からである。前回、宮澤賢治作の「十力の金剛石」についてふれた。宮沢賢治というと、夭折した不運な作家であり、農民の味方、農民の声の代弁者というイメージがあった。しかし実際は、裕福な実家の財力で好き勝手に生きていた、なかなかの「ぼんぼん」であったようだ。「十力の金剛石」では、かなりマイナーな宝石の名前も出ているので、思い描いていた賢治のイメージとは違っており、違和感があった。しかし、賢治は尋常小学校にいた頃より鉱物の収集が趣味だったよう だ。それに、賢治が20代前半であった1920年ぐらいには、父親に宝石の研磨や人造宝石の事業に乗るように勧めている。勝手に清貧のイメージを抱いていた自分が悪いのだが、宮沢賢治が宝石好きだとは、何だか裏切られた気分だ。賢治は1896年から1933年までの37年間、この世に生きた。イギリスの産業革命から30年代のアールデコ時代に重なる。研磨技術の発達もそうだが、人造宝石の技術が花開き始めた時代でもある。大掛かりに機材を用いて人造宝石が作られ始めた頃なのだ。
この時代は、日本に宝石や指輪などのジュエリーが広まった時期でもある。最初に指輪を身に着けはじめたのが、江戸時代後期の遊郭の女たちだったのは前にも書いた。ダイヤモンドは、もう少し歴史が進んだ明治・大正時代のハイソサエティの人々が身に着けた。そして、「ダイヤモンドは手の届かない美しい石」という印象を一般の人々に植え付けたのが、1897年(明治30年)に連載が始まった尾崎紅葉の「金色夜叉」だ。この文中で、金剛石に「ダイヤモンド」の仮名が振られたそうだ。そして、ヒロインのお宮が目がくらんだとされるのが、文中に出てくる300円のダイヤモンドの指輪。現在に換算するといくらぐらいかというと、当時10キログラムの白米が1円12銭だそう。今だと白米10キログラムで5000円ぐらいだろうか。そうなると単純計算で、当時の300円は今の150万円ぐらい。今では150万円の宝石などは珍しくないが、当時は値段もさることながら、ダイヤモンド自体が市場にほとんど出回っていなかった頃である。お宮が、見たこともない、七色に光る石に心を奪われる様は想像がつく。当時の読者は、小説の中で紡がれた言葉と想像力を総動員して、ダイヤモンドの美しさを脳裏に描いただろう。
金色夜叉のお宮は典型的な当時の女性を反映している。文明開化の最中で、これでもかこれでもかと押し寄せる西洋の圧倒的な技術力に対する恐れと憧れとを抱いていた。昭憲皇太后の「金剛石」という尋常小学校歌を聞き、金剛石とドレスを身に着け毅然とした表情の皇太后の写真に、どれ程の憧れを感じたのだろう。
昭和に生まれ平成を生きる私は、日常にタイヤモンドを楽しむという、昔では考えられなかった贅沢をしている。カフェでコーヒーを飲む時、食器を洗う時、娘の髪をとかす時。ダイヤモンドにひれ伏すことは無いが、ダイヤモンドの瞬きに心奪われる事は少なくない。トパーズでは得られない、心奪われるこの一瞬。やっぱりダイヤモンドだなと心新たにするのが、4月なのである。
(金子倫子)