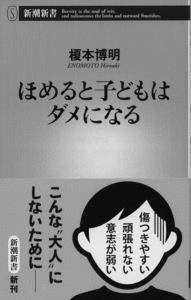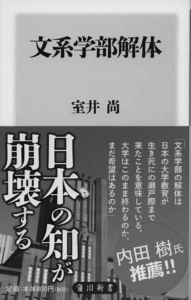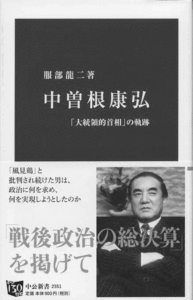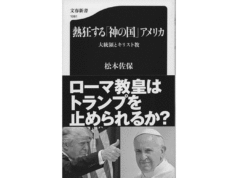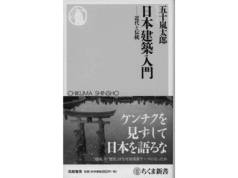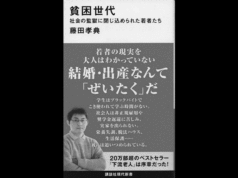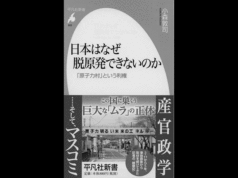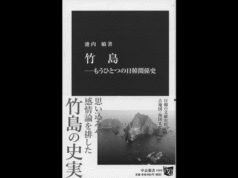2015年12月刊行から
日本では毎月100冊の新書が出版されている。「教養」から「時事」、「実用」まで多種多彩な新書群を概観することは、日本の最新事情を知ることでもある。日本で唯一の新書のデタベース「新書マップ」と連携したウェブマガジン「風」に連載の新刊新書レビューを毎月本紙で紹介する。
危険地域報道は必要か
2015年1月、「イスラム国」(IS)による邦人殺害事件の後、危険地域で取材活動を行うジャーナリストたちに対して、「そんな危険な所に行く必要があるのか」と非難の声が高まった。その声に乗じた政府は露骨な報道規制を敷くようになる。シリア取材を計画していたジャーナリストに外務省が旅券返納を命ずるという事件がそれを証明している。
政府による前代未聞のメディア統制と、それを妥当とする一部メディアの声に、「日本のジャーナリズムの危機」とフリーランス・新聞社・通信社など立場を超えて集まったジャーナリストたちによる一冊が、『ジャーナリストはなぜ「戦場」へ行くのか/ 取材現場からの自己検証』(危険地報道を考えるジャーナリストの会編、集英社新書)。ジャーナリズムとは何か、戦争報道はなぜ必要か、世界各地でテロ、紛争が続く今、考えさせられるテーマである。
「死人に鞭打つ」として日本ではあまり議論されないが、ジャーナリストが殉職した場合、取材日程やコーディネーターの選択等、他に選択肢はなかったのか、著者が知る限り同業者の間でもしっかりと検証されてはいないという。彼らに過失・失敗がなかったのかを検証し、今後の教訓として生かしていくことが、「英雄化」して讃えるよりも真の追悼になるのではないかと同業者たちは考えている。
『戦場記者/「危険地取材」サバイバル秘話』(石合 力著、朝日新書)(写真)の著者は朝日新聞の記者。本書でも、危険地取材における「邦人保護」と「報道の自由」のバランスをどうとるかという問題を正面からとりあげる。政府とメディアの関係として、昨年1月の邦人殺害事件の際、外務省がシリアから記者を撤退させようとしたやりとりを生々しく再現する。政府は「邦人保護」を、メディアは「報道の自由」をタテに、それぞれの立場を主張したまま平行線をたどるというこれまでの対応には限界がある。リスク回避のための具体的な対策をそれぞれの専門領域で高め合い、協力し合うことがこれからは必要になるのではと説く。
世界中を震撼させた2015年11月のパリ同時テロ。『イスラム化するヨーロッパ』(三井美奈著、新潮新書)の著者は、その10カ月前にパリを襲ったもう一つのテロ、政治週刊紙「シャルリー・エブド」襲撃事件を読売新聞パリ駐在員として目の当たりにしていた。「ホームグロウン・テロリスト」と呼ばれる、西欧育ちでありながら過激思想に共鳴する若者たちによる犯罪をどのように取り締まればよいのか。「シャルリー・エブド」事件の背景について、関係者に取材を重ねてきたものをもとに本書が生まれた。
「叱らない子育て」で傷つきやすい子が育つ?
『ほめると子どもはダメになる』(榎本博明著、新潮新書)(写真)では、ここ20年ほどよく聞かれるようになった「(叱らずに)ほめて育てる」という子育ての風潮に臨床心理学者が疑問を呈する。ちょっとしたことですぐに傷つく、意思が弱く頑張れない、教師や上司の注意や叱責に対して逆ギレ……。そのような若者が明らかに増え、学校や会社では従来の指導が通用しなくなってきている。忍耐する経験が少なく、叱られ慣れていないため、学校や職場、社会での適応に苦しむ子が増えている状況に著者は危機感をおぼえるという。
親や教師の権威が強い欧米の父性社会と、甘えが通用する日本のような母性社会では「ほめて育てる」ことの意味が大きく異なるのだが、その前提を見落としたまま「ほめて育てる」思想のみを表面的に取り入れたために、いま深刻な弊害をもたらしているのではないかという。
「ほめて育てる」という空気のなか厳しく叱られることを知らずに育った世代が、今度は親となって子育て側にまわりはじめる。「ほめて育てる」の弊害が深刻化するのはまさにこれから、と懸念している。
『研究者としてうまくやっていくには/組織の力を研究に活かす』(長谷川修司著、ブルーバックス)の著者は物理学者。大学だけではなく企業の研究所に所属した経歴ももつ。研究者をめざす若者に対し、「研究とは、答えのわかっていない課題を考えること」であり、答えの決まっている高校、大学までの『勉強』と、大学院からの『研究』は全く違うものと説く。また、研究者といえども、普通の職業の一つ。周囲の人とうまくコミュニケーションがとれなかったり、自分の専門分野のことしか語れないのでは(一般の社会人と同様に)うまくやっていけない。そうした「研究以外」のノウハウやスキルの重要性が若い世代にあまり認識されていないのでは、と指摘する。
著者の専門である理工系の研究者をイメージした記述が基本となってはいるが、人文・社会科学系の研究者をめざす人にも参考になる部分は多い。
一方、いま日本の大学教育、特に文系の領域がこれまでにないほどの危機、崩壊寸前にあると警鐘を鳴らすのが『文系学部解体』(室井尚著、角川新書)(写真)。2015年6月、全国の国立大学に対して、人文科学系学部、教員養成系学部など「文系」学部・学科の縮小や廃止を「要請」する文科相名による通達があった。(文科省は通達を「誤解があった」と一部否定している。)目に見えた成果がすぐには期待しにくい文系学部を軽視した政府の政策を著者は徹底的に批判する。
大学の役割とは、自分の頭で批判的に考え、行動する人々を育成し、社会に送り出していくことではないか。タテマエでは「大学の自主的な取り組み」と言いながら、実際は判で押したように決まりきった「改革」を一律に押し付けてくる国や文科省の「大学改革」をこれ以上進めさせてはならない。「大学は会社や工場ではない」と強く主張している。
政治・社会の「自由」とは何か
中国の一部でありながら、オリンピックに代表を送り、独自の通貨を発行する香港。香港は国なのか、地域なのか、都市なのか。『香港/中国と向き合う自由都市』(倉田 徹、張 イクマン著、岩波新書)は、1997年に中国へ返還されてからも変わり続けている「自由都市」香港の今を、日本/香港の二人の専門家が解説する。2014年秋、香港民主化を求めた大規模なデモ「雨傘運動」がなぜ起きたか、香港の政治・社会の「自由」の現状を歴史背景をふまえて解読する。
『中曽根康弘/「大統領的首相」の軌跡』(服部龍二著、中公新書)(写真)は、1918年生まれ、今年98歳を迎える元首相の評伝。2003年に衆議院議員を引退してからも政界は引退せず、超高齢ながら強い影響力を保ち続けている。いまや戦後史を通して語ることができる政界唯一の存在である中曽根本人に、インタビューを重ねた著者が、首相退任から30年近くを経て情報公開請求などで入手できるようになった基礎文献なども加えて書き上げた。
少子高齢化日本の行く末
総務省統計局が毎年恒例で年末に発表する「申年生まれの人口推計」( 平成28年1 月1日現在)の数字を見て驚いた。申年生まれの人口は991万人、年代別(今年12歳の平成16年生まれ~96歳の大正9年生まれまで)にみると、最も多いのは昭和43年生まれの182万人(今年48歳:男女計)だが、昭和19年生まれは159万人(今年72歳:男女計)で、最も若い平成16年生まれは110万人。後期高齢者に近い72歳の人口が、将来を担う12歳の人口よりも50万人近く多い。少子高齢化とはそういうことなのだ、と年始早々改めて考えさせられた。
全国の自治体を騒然とさせた「地方消滅」論の増田寛也氏らが次に打ち出してきたのは『東京消滅/介護破綻と地方移住』(増田寛也編著、中公新書)。
要介護高齢者の激増で、医療・介護関連の人材がこれ以上東京圏に集中すれば、「地方消滅」にさらに拍車がかかるとし、激増する要介護者の受け皿不足解消のためにも、地方への移住を含めた「解決策」を提示している。高齢者の地方移住という「解決策」を「姥捨て山」と安易に批判するのではなく、新しい発想で危機に立ち向かうべき、としている。
『ルポ 老人地獄』(朝日新聞経済部著、文春新書)では、まさにその「現代の姥捨て山」というべき状況が、団塊の世代が後期高齢者となる「2025年」を待たずに進行している様子を生々しく伝える。
『ルポ 消えた子どもたち/虐待・監禁の深層に迫る』(NHKスペシャル「消えた子どもたち」取材班著、NHK出版新書)は、全国初の大規模アンケート調査で明らかになった、貧困や虐待など、保護者の問題により保育所や学校に通えず社会から「消された」子どもたちの実態を伝える。子どもを社会から消したまま死なせてしまう悲劇を繰り返してはならない、とすべての大人に向けてうったえかける。
(連想出版編集部 湯原葉子)