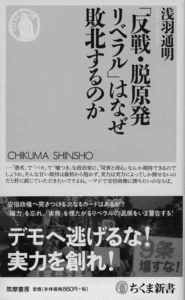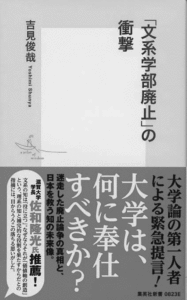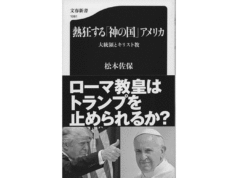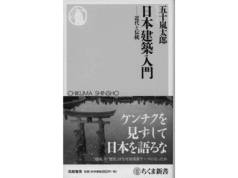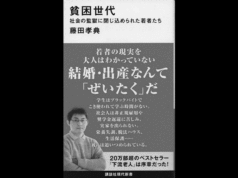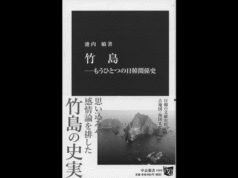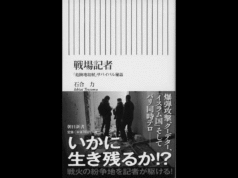2016年2月刊行から
日本では毎月100冊の新書が出版されている。「教養」から「時事」、「実用」まで多種多彩な新書群を概観することは、日本の最新事情を知ることでもある。日本で唯一の新書のデタベース「新書マップ」と連携したウェブマガジン「風」に連載の新刊新書レビューを毎月本紙で紹介する。
東日本大震災から5年
日本の「原子力村」は世界一大きい、と断言するのが『日本はなぜ脱原発できないのか/「原子力村」という利権』(小森敦司著、平凡社新書)(写真)の著者。原発事故後、脱原発を求める多くの世論の一方で、政府が原発再稼働路線を押し進めることができる背景に、日本の巨大な「原子力村」の存在がある。この「村」は電力会社だけではなく、産業界・財界、官僚、政治家、学者、メディアもとりこみ、巨大で強力な「原子力複合体」とも言える。朝日新聞経済部出身の著者は、被災者や脱原発派を追うのではなく、原発推進派や原発を支える経済構造を追うのが自分の役割だとして、取材を重ね、記事にしてきた。本書はその記事を再構成し、大幅加筆した。
『リンゴが腐るまで/原発30 ㌔圏からの報告 記者ノートから』(笹子美奈子著、角川新書)の著者は、読売新聞記者として2013年から2年間にわたり福島県で東日本大震災と原発事故の被災者を取材してきた。お年寄りの孤独死、アルコール依存症、家庭の崩壊、国などから受けられる補助金の額が異なることによって生じる地域住民間の不和、いつか元の地域に戻るのか、避難先に移住するのか。福島で見聞きしたものはその10 年前、著者が2004年新潟県中越地震の被災地の取材で見聞きした光景とそっくりだったという。
『ルポ 母子避難/消されゆく原発事故被害者』(吉田千亜著、岩波新書)では原発事故後、政府による避難指示がない地域から、放射線による影響を避けるために「自主的に」避難している人のうち、主に母子で避難している人々に焦点をあてている。この5年間どのような思いで暮らして来たのか、今何を考えているのかを著者が聞き取っている。
『「反戦・脱原発リベラル」はなぜ敗北するのか』(浅羽通明著、ちくま新書)(写真)は、「若者を巻き込んだ楽しくかっこいい社会運動」を礼賛したメディアと知識人たちの言動について、リベラル勢力を劣化させるものだ、と実名をあげて批判していく。3・11 以降、脱原発や反戦を求めたこれまでにないスタイルのデモが多くの参加者を集め、その動きに賛同する知識人や、これらの動きを大きく好意的に報道するメディアがあった。しかし評論家である著者は、デモの目的と手段をいつの間にかすり替えるようなリベラル知識人・文化人の言説に対し、本来の目的だったはずの反戦・脱原発をどれだけ本気で考えているのか、本来の目的のためにデモに参加した人たちをバカにした話ではないか、と厳しく批判している。
M7級以上の大地震が首都東京を直撃したらどうなるか。その被害への備えは十分か、と問いかけるのが『首都直下地震』( 平田直著、岩波新書)。著者は東京大学地震研究所の地震予知研究センターで地震予知の研究をしている。最新の地震学でも、現時点では首都圏の地震予知はできないというのが現実だが、首都圏のどこかでM7 以上の大地震が発生することは間違いない、と再三強調している。
『震災学入門/死生観からの社会構想』(金菱 清著、ちくま新書)では、東北被災地に密着してきた社会学者が、これまでの科学的・客観的な災害対策を、被災者、弱者の視点から見直す必要がある、と主張する。津波リスクの高い被災地で、高台移転や巨大防潮堤の建設に反対する声がなぜ起きるのか。そこに住んでもいない者が堅牢な巨大防潮堤建設を推進するような「生命第一優先主義」は本当に正しいのか。東日本大震災がわれわれに問いかけているのは、災害リスクと今後どのように共存していけばよいのかという課題である。
時代によって変わる表現の規制
日本では初めてという本格的な「春画展」が2015年に東京で開催され、多くの人が訪れ、マスメディアでも好意的に報道された。その一方で、展示される作品の一部を紹介した週刊誌の特集記事について、「猥褻物にあたる可能性がある」として警視庁から厳重な「指導」を受ける事となったという。『エロスと「わいせつ」のあいだ/ 表現と規制の戦後攻防史』(園田 寿、臺 宏士著、朝日新書) では、今日本の性表現はどうなっているのか、エロスと猥褻の境界線はどこにあるのか。児童ポルノ問題などに詳しい弁護士( 園田氏) とジャーナリスト(臺氏)による共著。児童ポルノ規制やサイバーポルノの実態等にもふれている。
『「文系学部廃止」 の衝撃』(吉見俊哉著、集英社新書)(写真)は、東京大学教授で同大学の副学長も務めた著者によるもの。2015年6 月に文科省が出した「国立大学法人等の組織及び業務全般の見直しについて」という「通知」を機に、突如として世論を賑わした「文系学部廃止」論争について扱う。
本書ではその経緯について、事実関係を整理して解説していく。その上で「文系は役に立たないから要らない」という議論だけではなく、「文系は役には立たないけれども価値がある」という議論も批判している。
一般人の「常識」とかけ離れがちな専門家の視点
『非常識な建築業界/「どや建築」という病』(森山高至著、光文社新書)のタイトル、「どや建築」という語は、著者の造語。斬新さや奇抜さばかりを追い求めた建築家による、周囲の環境とまったく調和しない、「威圧的な『どや顔』をした建築」だという。建設費の暴騰が問題となり白紙撤回されることになった新国立競技場(ザハ案)がまさにその典型だ。建物に要求される用途に応じた機能とはかけ離れた、「とにかく新しく独創的なものをつくらなければ評価されない」という建築家たちの「幻想」(あるいは強迫観念) が「どや建築」を生んできたと指摘する。
同じく2015年に大きな騒動となったのが、盗作疑惑が持ち上がり、炎上、後に白紙撤回となった2020年東京オリンピックのエンブレム問題。『だからデザイナーは炎上する』( 藤本貴之著、中公新書ラクレ)は、この騒動を題材とし、インターネット時代におけるデザインのあり方を論じている。
デザイナーは技術者であって、アーティストであってはならないはずだが、多くのデザイナー自身がそこを勘違いしているのがそもそもの問題の始まりではないか、という。
『本物の英語力』(鳥飼玖美子著、講談社現代新書)は、ネイティブ並みに英語をつかいこなす一部エリートと、英語に苦手意識をもつ人や、英語が嫌いであきらめてしまっている脱落組のあいだに「英語格差」というべき格差が生まれ始めている現状に危機感をおぼえている。かといって、「英語学習は子どものうちからやらなければ手遅れ」「ネイティブ並みの発音でなければ恥ずかしい」「いくらやっても英語はできるようにならない」などと、トラウマのように引きずって英語を学習しないでいるのはもったいない。英語ができるようになりたいと内心思いながらも、英語をあきらめかけている人にむけ、新しい視点での英語学習法を紹介している。
『翻訳百景』(越前敏弥著、角川新書) の著者は、世界的にヒットし日本でも大ベストセラーとなった、長編推理小説『ダ・ヴィンチ・コード』(ダン・ブラウン著)の日本語訳などで知られる人気翻訳家。ミステリーだけでなく児童書の訳書もあり、幅広い読者をもつ。本書では、文芸翻訳とはどんな仕事なのか、編集者の役割とは何か、など翻訳の現場を具体的に紹介している。
『ニッポンの文学』(佐々木敦著、講談社現代新書)は、同じ著者による『ニッポンの思想』『ニッポンの音楽』に続く三冊目のシリーズ。本書で著者は、多くの日本人の間で何となく共有されている「文学」と「小説」との違いについて述べている。海外でも「Literature(文学)」と「Fiction(小説)」というほぼ同様の違いに相当する言葉がないわけではない。しかし、日本においては「文学」という言葉がことのほか強い意味をもつ。その理由に「芥川賞」の存在をあげている。「文学」と「文学以外(その他の小説)」を分ける定義は何なのか。著者は、これまで「文学」根拠なく権威づけられてきたが、今や「芥川賞」があることでかろうじて維持されている制度にすぎないのではと考える。
『トウガラシの世界史/ 辛くて熱い「食卓革命」』(山本紀夫著、中公新書) (写真)は、植物学者による、トウガラシの魅力と役割に注目した珍しい一冊。トウガラシは15 世紀末、コロンブスによって原産地の中南米からヨーロッパに持ち帰られ、ヨーロッパからアフリカやアジアなど世界各国にもたらされた。今や中南米原産とは想像できないほど、500年ほどの期間に世界中で利用・栽培され、食文化に欠かせないものとなっている。朝鮮半島にトウガラシが伝わり、キムチにトウガラシが使われるようになったのは今から250年ほど前のことでしかない、というのは驚きだ。
(連想出版編集部 湯原葉子)