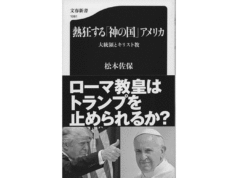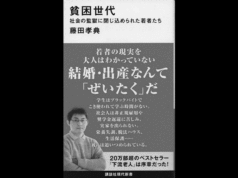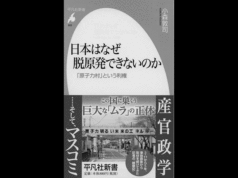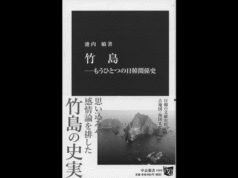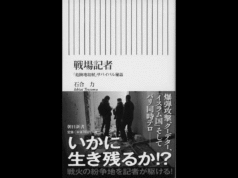本では毎月100冊以上の新書が出版されている。「教養」から「時事」、「実用」まで多種多彩な新書群を概観することは、日本の最新事情を知ることでもある。日本で唯一の新書のデータベース「新書マップ」と連携したウェブマガジン「風」に連載の新刊新書レビューを毎月本紙で紹介する。
建築に見る「日本らしさ」とは
ザハ・ハディド氏による当初のデザイン案が白紙撤回され、迷走をきわめた新国立競技場建設問題。仕切り直しのコンペが発表された際、「日本らしさを表現すること」「木材を使うこと」という項目が新しい条件として追加され、国際コンペでありながら日本語で提出することになっていた。建築史、建築批評の第一人者による『日本建築入門/近代と伝統』(五十嵐太郎著、ちくま新書)(写真)では、結果的に二人の日本人建築家の応募2案から選ぶことになった仕切り直しのコンペは、外国人の参加を制限しようとしたと思われても仕方がない、と指摘する。
本書では、建築における「日本らしさ」、「ナショナリズム」がどう評価されてきたかを振り返る。特にオリンピックと万博において、日本がどのような「日本らしさ」を海外に見せようとしてきたかという考察も興味深い。
戦後復興期から高度経済成長期、バブル経済とその崩壊……。『丹下健三/戦後日本の構想者』(豊川斎赫著、岩波新書)は、戦後日本の歩みを語る際に欠かせない重要な建築を数多く生んだ建築家・丹下健三に注目する。個人住宅をほとんど設計せず、公共建築を通じて国家・社会・都市の理想像を目に見えるようにした丹下。「丹下シューレ(丹下学派)」と呼ばれた門下生のうち槇文彦、磯崎新、黒川紀章ら8人の有名建築家にもスポットを当て、「丹下の何を受容し、いかに、乗り越え、現在の問題にどう対峙しているか」を紹介する。
『人が集まる建築/環境×デザイン×こどもの研究』(仙田満著、講談社現代新書)の著者は、1968年、26歳の若さでデザイン事務所「環境デザイン研究所」を立ち上げた。新広島市民球場、秋田市の国際教養大学図書館、保育園や科学館、自然博物館、などこどもも大人も「また来たくなる」空間を数多く設計してきた。こどもたちが元気に育ち、大人も町も健康でいられるための、建築を含めた環境のあるべき姿とはなにか。全国各地にわたる実例をもとに提示している。
プロパガンダ、マインド・コントロール、メディアコントロール
1950年代から国策として国が主導し、政官学と電力業界を中心とする経済界が展開した原発推進PR活動は、実施された期間と巨額の予算から考えて、「世界でも類がないほどの国民扇動プロパガンダだった」と言い切るのが『原発プロパガンダ』(本間龍著、岩波新書)。著者は、「博報堂」で約18年間営業現場に勤務した経験をもつ著述家。東日本大震災による福島第一原発事故が起きるまで定着していた原発の「安全神話」はどのようにつくられ、維持されてきたのか、広告、メディアの側面から振り返る。
マインド・コントロールといえば、「洗脳」とも呼ばれ、心理的に他人を支配し、操作するというネガティブな側面が有名。だが、一方で、自分の心理状態をコントロールすることで、より高いパフォーマンスを実現したりする有用な手段にもなり得る。『マインド・コントロール/増補改訂版』(岡田尊司著、文春新書)によれば、いまやカルト、反社会的集団、ブラック企業だけでなく、コマーシャルや広告、営業マンやマスコミなどあらゆる組織のなかでもその技術が応用されているという。精神科医の著者はマインド・コントロールの原理と応用を解説し、マインド・コントロールを解く技術を知っておくことの重要性をうったえる。
『安倍官邸とテレビ』(砂川浩慶著、集英社新書)は、第二次安倍政権によるメディア介入について、放送を中心としたメディア政策に詳しい研究者がそのスタート時から3年間を振り返る。
メディア経営幹部との頻繁な会食、登場メディアの露骨な選別、NHK人事への介入、総選挙報道への注文、自民党本部への前代未聞のテレビ局呼びつけ、そして電波停止をちらつかせるという脅し……。安倍政権によるテレビに対するさまざまな形の圧力について解説していく。安倍首相が国会議員となった1993年以降のメディアとの関わりも、現在の状況を読み解く上で興味深い。表現の自由とは誰のためのものか、テレビメディアは権力監視の役割を果たす事ができるのか、考えさせられる。
創価学会のめざす宗教的理想を実現するために政治の世界に進出して50年という公明党。『公明党/創価学会と50年の軌跡』(薬師寺克行著、中公新書)は、国政選挙では常に700万票以上を獲得し、巨大な政治勢力である公明党について、結党から今日にいたるまでを公式記録や資料等をもとに分析している。
ここまで大きな権力をもっている政党でありながら、熱烈に支持する人々と、無関心あるいは拒絶の態度をとる多くの人々との距離はかけ離れている。公明党の判断が国民の生活に直接影響を与える局面は多く、支持しない人々こそ、党のことをもっとよく知り、その活動をきちんと監視していくべきではないだろうか、と主張している。
若者が変えていく未来
『18歳からの民主主義』(岩波新書編集部編、岩波新書)は、今夏の選挙から初めて選挙権をもつことになる18歳、19歳、あるいはより若い世代に向けて、「民主主義とはなにか」「選挙は何のためにあるのか」「政治をどう考えたらよいか」を伝えるために、さまざまな分野の第一人者、専門家から寄せられたメッセージを集めたもの。もちろん、若い世代以外にとっても、さまざまな観点から一票の重みを考えさせられる一冊となっている。
『ブラックバイト/学生が危ない』(今野晴貴著、岩波新書)は、『ブラック企業/日本を食いつぶす妖怪』(文春新書、2012年)の刊行以降も、将来ある若者の使い潰しがますます酷くなっていることを告発する。
学業よりもアルバイトを優先するように強制され、休みのない過密シフトで「授業に出られない」「試験が受けられない」「留年してしまった」などのケース、業務上のミスに対して罰金を取られる、商品の買い取りノルマに泣く泣く自腹を切ることも珍しくないという。かつてのように小遣いのための気楽で自由なものではなくなっている、学生アルバイトの深刻な状況を報告する。「ブラックバイト」の見分け方やトラブルに巻き込まれた場合の具体的な対処法も提示している。
2015年、東京都渋谷区と世田谷区で、日本で初めて同性パートナーシップを認める条例が誕生した。その後も、同様の動きが他の自治体にも見られるという。日本でも世界でも、LGBT、セクシャルマイノリティの権利に関するニュースが報道されることが増えてきている。『恋の相手は女の子』(室井舞花著、岩波ジュニア新書)は、女性二人で結婚パーティーを挙げた著者が、自らの体験やさまざまな当事者のエピソードを交え、多様な生き方を認める社会への希望をつづる。
妻に「死んでほしい」と言われないためには……
「亭主元気で留守がいい」というCMのキャッチフレーズが流行したのは1986年。当時の一般的なサラリーマンと比べれば、家事育児にはるかに積極的に関わっているように見える現代の「イクメン」たちだが、妻から見れば「それでやっているつもり?」と評価は必ずしも高くない。
『夫に死んでほしい妻たち』(小林美希著、朝日新書)には、妻の希望や理想からズレまくった言動を繰り返し「いっそ死ねばいいのに」とさえ思われている夫に対する妻の怒りが世代を問わず炸裂している。妻が望むような家事や育児をしたくてもできない労働環境を強いられている男性側の声もきちんと拾い上げ、すれ違いをうめるためのヒントも示している。
明治近代の成立と、戦後復興・高度経済成長という二つの大きな急坂を登りきった日本人は、これから成長の止まった長く緩やかな衰退の時間をどう耐えていけばよいか。『下り坂をそろそろと下る』(平田オリザ著、講談社現代新書)は、劇作家の著者が、成長をしないということを前提にしてあらゆる政策を考え直していくことの重要性を説く。
親から子へと体型や性格が似るのと同様に、知能や運動能力、音楽的才能などが遺伝するケースは昔からよくあることとして語られる。しかし、逆に考えると、「頭が悪い」「運動ができない」「音痴である」「アルコール中毒である」などのマイナスと思われる要因も遺伝する場合も多くあるはずだが、そうしたことを発言することは社会的に強いタブーとされている。
『言ってはいけない/残酷すぎる真実』(橘玲著、新潮新書)は、遺伝よりも環境で人は変えられる、すべての人は努力すれば報われるはず、などという「きれいごと」にとらわれず、「努力は遺伝に勝てない」「見た目で人生は変わる」などの「言ってはいけない」とされる不愉快な真実も直視せよ、とうったえる。
(連想出版編集部 湯原葉子)