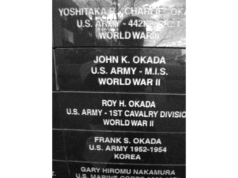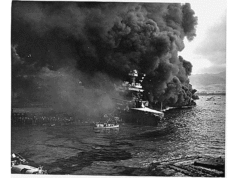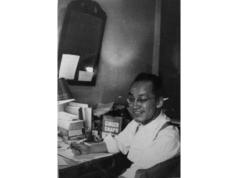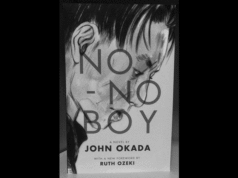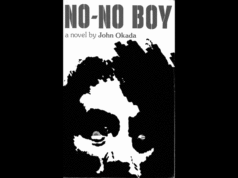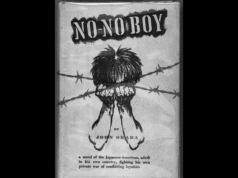太平洋戦争を挟みアメリカで生きた日系アメリカ人二世、ジョン・オカダ(John Okada)が残した小説「ノーノー・ボーイ(No-No Boy)」。1971年に47 歳で亡くなった彼の唯一の作品は、戦争を経験した日系アメリカ人ならではの視点でアイデンティティをはじめ家族や国家・民族 と個人の在り方などさまざまなテーマを問う。いまも読み継がれるこの小説の世界を探りながらその魅力と意義を探っていく。
一昨年アメリカで出版された、新版の『No-No Boy』には、これまでになかった新たな序文がつけられた。1957年のオリジナルは小説のみで、1976年の復刊にあたっては、そのいきさつなどをまとめた序文とあとがきが加わり、新版でさらに新版用の序文がついたことになる。
解説的に後ろにまとめて掲載されるのではなく、これだけいろいろなものを前後につけて構成されると、小説としては読みにくいと思われるかもしれない。しかし、新版にあたっての新たな序文がこの作品の今日的な意味を説き、また新たに明らかになったこともあり、その意義はあるだろう。
序文を書いたのは、日系アメリカ人の女性作家のルース・オゼキ(Ruth Ozeki) である。2013年に発表した小説『A Tale for the Time Being』は、日本でも翻訳されて「あるときの物語(上下)」(田中文訳)として翌年早川書房より出版された。
物語は、カナダの島に暮らす女性作家が、日本から流れ着いた弁当箱のなかから、東京の女子中学生の書いた日記を発見し、彼女がいじめに遭い自殺をほのめかしていることなどを知る。その日記を通して時間を超えた壮大な物語が見えてくるというもの。
早川書房は、以下のように著者を紹介している。
ルース・オゼキ(Ruth Ozeki): 「アメリカのコネチカット州で、アメリカ人の父と日本人の母のもとに生まれる。スミス・カレッジにて英文学とアジア研究で学位を取得したのち、文部省の留学生として奈良女子大学大学院で日本古典文学を学ぶ。1985年に帰国し、ホラー映画やテレビ番組の制作を経て、映画を撮りはじめる。手がけた映画作品は各地の映画祭で上映されるなど高い評価を受けた。1998 年にデビュー長篇『イヤー・オブ・ミート』を発表し、大型新人として注目を集める。2003年に第二作All Over Creation を発表。2013年に刊行した第三作にあたる本書は、有力紙誌に絶賛され、ブッカー賞最終候補となった。2 0 1 0 年に曹洞宗で得度。現在カナダのブリティッシュコロンビア州とニューヨーク市で暮らす。」
オゼキは「ノーノー・ボーイ」が出版された前年の1 9 5 6 年生まれで、ジョン・オカダとは父子ほどの年齢差である。
「D e a r J O H N OKADA」( 親愛なる ジョン・オカダへ) と、いう書き出しで、オカダに宛てた手紙の形をとって12 ページにわたってつづっている。その筆致は親愛と尊敬とそして、同じ作家として同情の念がうかがえる。
戦争を挟んでの厳しい環境のなかで日系人を主人公とした小説「ノーノー・ボーイ」については、「栄誉ある最初の日系アメリカ人小説」であり「アジア系アメリカ文学の不朽の名作のひとつ」という評価の上にたって、小説について、オカダについて、そして同じ日系人として自分自身がこの小説に出合ったことで受けた衝撃などをまとめている。
最初に小説が出版された当初はほとんど無視されたことや、手厳しい批評を受けたり、悪文だと言われたり、文学ではないといった批評もあったことをあげ、オカダが自分の作品を失敗と思ったのではないかと思いやる。
また、出版された当時の時代背景として、まだ戦争の傷跡が日系人の中に残り、必死で社会に同化しようとしていた時期に、この作品は日系人にとってラディカルに思えて評価されることはなかった事実をあげる。
しかし、それから20 年経って人種差別などに対する世間の関心も高まり、「ノーノー・ボーイ」は復刊され評価される。そしていまに至るまでずっと読み継がれるという偉業を成し遂げた。だが、この成功を知らずに亡くなったオカダに対して深い同情の念を示す。
ルースの祖母は戦時中収容された経験があり母親は自宅軟禁された。しかしアジア人が少ない東海岸で育ったルースは、自分が日系人である意識がなく日系アメリカ人の文化活動にはたいして興味を持たなかった。復刊されたときは20 歳で、この時点でも『ノーノー・ボーイ』を読まなかった。ようやくそれを読んだのは40 代になってからだという。
そして衝撃を受ける。アメリカの日系人はおとなしく、従順で、文句も言わず必死に戦後を生き抜き社会的に成功していった。こうしたいわば神話が定着していき、ルース自身もそう思ってきたのが、『ノーノー・ボーイ』によってこうしたステレオタイプ化された日系人のイメージは覆された。また、日系人の怒りや複雑な心境を世に知らしめたと評価する。
序文はオカダの経歴についても詳しく述べている。そのなかで彼の弟で画家のフランク・オカダの言葉から興味深い点を紹介する。オカダは故郷のシアトルでの生活を好んでいたが、小説を書く前に一時デトロイトに移った。「もしそのままシアトルにいたら創作はできなかった。自分を孤立させ客観的にものごとを見るために小説の舞台であるシアトルを離れたのだろう」という。
フランクの話からのもう一つ興味深い点は、オカダが書き残したという一世を主人公にした未完の作品の原稿についてだ。復刊時に巻末に添えられたあとがきで、フランク・チンは、この原稿や残されたメモなどは、未亡人のドロシーがオカダの死後UCLA (カリフォルニア大学ロサンゼルス校) のジャパニース・アメリカン研究プロジェクトに寄贈しようとしたところ断られたので焼き捨ててしまったと書いている。
しかし、フランクによればUCLAは当時日本人一世の日本語による資料を受けつけていたので受け入れられなかったのであり、また、オカダの第二作は当時まだ調査の段階で実際は書きはじめていなかったという。いずれにしても残されたものはなにもなくなったという事実 は変わらないことをルースは嘆く。
最後に、オカダによる、「フィクションだけが人々の希望や恐れや喜びや悲しみをしっかり記録できる」という言葉を紹介し、それへの賛同を示している。
(敬称略)
(川井 龍介)
筆者プロフィール: ジャーナリスト。慶應大学法学部卒。毎日新聞記者などを経て独立、ノンフィクションを中心に執筆。「大和コロニー『フロリダに日本を残した男たち』」(旬 報社)、「『十九の春』を探して」、「122 対0の青春」(共に講談社) などど著書多数。「No-No Boy」の新たな翻訳を手掛ける。この夏、『ノーノー・ボーイ』の新訳を旬報社から出版予定。