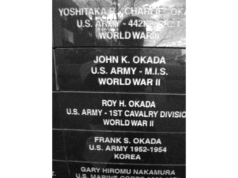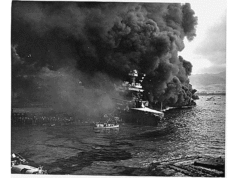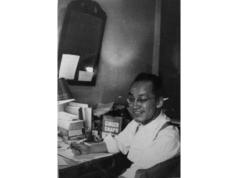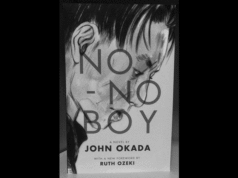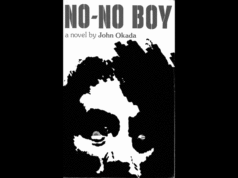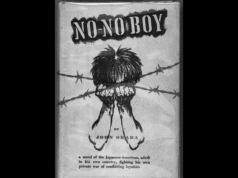第 14 回 六章、死を予感するケンジの悲しみ
太平洋戦争を挟み米国で生きた日系二世、ジョン・オカダ(John Okada)が残した小説「ノーノー・ボーイ(No-No Boy)」。1971年に47歳で亡くなった彼の唯一の作品は、戦争を経験した日系人ならではの視点でアイデンティティをはじめ家族や国家・民族と個人の在り方などさまざまなテーマを問う。いまも読み継がれるこの小説の世界を探りながらその魅力と意義を探っていく。
著者のジョン・オカダが、心優しい日系人家族の姿を、美しくも悲しく描く印象的な章が、物語も中ほどにさしかかった第六章だ。
戦争で片脚を失ったばかりか、傷んだところが悪化してきたケンジは、シアトルから再びポートランドの復員兵病院へ行くことになる。これまでとちがいもう二度と戻って来られない予感がするケンジは、家族に別れを告げる。
一世の父の後悔
母はかなり前に亡くなり、父が長い間職人として男手ひとつで3男3女を育ててきた。アメリカで一旗揚げようとやってきた一世の父は必死に働き、その結果子供たちは二世として立派にアメリカ社会で生きている。
子供たちは父を敬い、父はまた子供たちを誇りに思っているこのほのぼのとした家族は、みんなケンジのことを案じていた。ケンジも傷ついた自分に対する家族の心遣いを十分理解していた。
とくに、父が自分のことを愛し心配していることは痛いほどわかっていた。多くの日系アメリカ人の若者が「日系」であるがゆえに、アメリカ人である証しを立てようと戦地に赴き傷ついたことを考えれば、なかには日系であることを呪い、怨む二世もあったかもしれない。
しかし、ケンジは露ほどもそんなことは思っていない。ケンジはアメリカのために戦って死ぬ覚悟で戦争に行った。その気持ちを著者は「すでに彼のものであるはずのアメリカ人としての権利を、本当に享受する資格があることを証明するために」とあらわす。
だが、ケンジの父は息子に対して申し訳ないという気持ちがあった。自分が日本人だから息子がその報いを受けたのではないかと。父がケンジにこう言う。
「私がアメリカに来たのは、金持ちになって日本の村に帰って、ひとかどの者になるだめだった。欲が深くて野心に満ちていて高慢だった。私はちゃんとした人間ではないし頭もよくなかった。ただ若くて愚かだった。だからおまえがその報いを受けた」
これに対して、ケンジは嘆くように言う。
「何の話をしてるんだい。……そんなことまったくありゃしないよ」
父はまた、ケンジが軍に志願すると言ったとき、もし自分がやめろと言っていたならこんな目に遭わなかったのかと自問し、ケンジにも問う。が、そんなことはないとケンジは否定する。もし仮に戦争に行かなかったら、父とは友達のように語ることもなかったとまで言う優しさがケンジにはあった。
孤独を抱えて家族と別れる
ケンジを囲んでディナーがはじまり、みんながケンジを気遣うなかで、弟のトムが兄のことを案ずるあまり、ケンジを治療している医者たちをなじる言葉をはく。これに対してケンジが大丈夫だと安心させる。
ディナーが終わり、嫁に行った姉妹も家族連れで帰って来て、小さな子供たちもまじって野球観戦をしながらにぎやかな家族団らんとなる。そこから一人そっと裏口に出たケンジは、みんなの楽しそうな語らいを聞く。このあたりの描写は、読む者にケンジの孤独と寂しさをひしひしと伝える。
ほんとうはケンジの容態がよくないことを父だけはわかっていた。ひとりになったケンジと父とのやりとりのなかで、ケンジは「怖いよ」と正直な気持ちを話す。
父だけに別れを告げ、家族の団らんをよそにケンジはその夜、家を出てポートランドへ向かおうと車に乗込んだ。別れの場面を著者はこう書く。
「どうしようもないほど、父のところへ戻ってもう少し一緒にいたいという気持ちに駆られ、ケンジの手はドアの取っ手を探った。その瞬間、父はさよならと手をゆっくりひと振りした。急いでケンジは車をバックさせて家を出た」
子供ができ、一世は変わる
六章では、ケンジの父の気持ちとして、移民した一世が月日の経過とともにどのように変わっていくかがあらわされる。
「……自分が日本に帰るという考えを捨ててしまったのはいつのことだったか、父はとうの昔に忘れてしまっていた。ただ、それが、愛する気などまったくなかったこの国が突然自分の一部になりはじめたときだったことだけは覚えていた。国は子供たちの一部であり、子供たちが話すことや喜びや悲しみや希望のなかに国を見て感じ、そして自分は子供たちの一部だからだ。自分がアメリカに持ってきたばかげた夢が消えていくなかで、この異国で得られた人生の豊かさが過去への憧れを壊してしまった」
また、アメリカで生まれ、アメリカ文化に染まり育ちアメリカ人になっていく子供たち(二世)と、一世の間の大きな文化的な隔たりが描かれる。
話を物語の筋に戻すと、家を出たケンジは、ポートランドへ同行するイチローを迎えに行く前に、なじみのバー、クラブ・オリエンタルに立ち寄る。イチローと前夜訪れその後いざこざがあった店で、小説の最後にも登場する旧日本人町の象徴的なバーだ。
ここで束の間の安らぎを得て、夜中にイチローの家を訪ねるが、そこでイチローの母の奇行を目にする。日本からの手紙を読んでおかしくなったと思われる姿だった。
イチローにもわかっていたが、それを尻目にケンジとともに真夜中のドライブに出てポートランドを目指す。途中、スピード違反で白人のパトカーにつかまり、警官から見逃してやるからと賄賂をよこせと暗に言われる。ケンジはこれを突っぱねてチケットをもらう。入院したらそれで最後だと感じているケンジにはどうでもいいことだったからだ。
そういうケンジの予想と覚悟を聞いたイチローはショックを受ける。朝になりポートランドの病院に着く。ケンジは入院し、イチローはポートランドの街にでた。
(川井 龍介)
筆者プロフィール:ジャーナリスト。慶應大学法学部卒。毎日新聞記者などを経て独立、ノンフィクションを中心に執筆。「大和コロニー『フロリダに日本を残した男たち』」(旬報社)、「『十九の春』を探して」、「122対0の青春」(共に講談社)などど著書多数。「No-No Boy」の新たな翻訳を手掛ける。この夏、『ノーノー・ボーイ』の新訳を旬報社から出版予定。
編集部より
本記事は全米日系人博物館が運営するウェブサイト「ディスカバーニッケイ(www.discovernikkei.org)」からの転載になります。