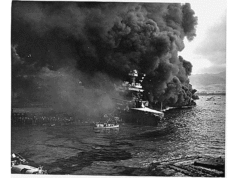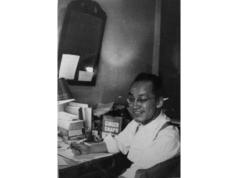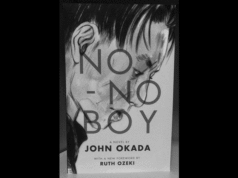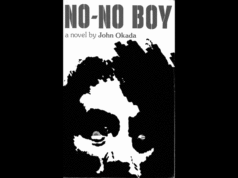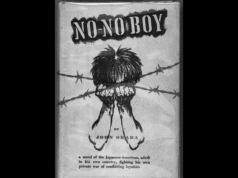太平洋戦争を挟み米国で生きた日系二世、ジョン・オカダ(JohnOkada)が残した小説「ノーノー・ボーイ(No-NoBoy)」。1971年に47歳で亡くなった彼の唯一の作品は、戦争を経験した日系人ならではの視点でアイデンティティをはじめ家族や国家・民族と個人の在り方などさまざまなテーマを問う。いまも読み継がれるこの小説の世界を探りながらその魅力と意義を探っていく。
イチロー・ヤマダの母は、戦争が終わっても日本が負けたと信じられずにいる。その頑迷さと狂信性にイチローは腹を立て、同時にそんな母の間違いを正さず、あたらず触らずの態度をとっている父の態度にも腹を立てていた。
5章では、この母に対して初めて父が、正気に戻るように迫る姿が描かれる。母のもとには、日本で暮らす姉や親せきから、戦争によって生活が苦しく物的な援助をしてもらえないだろうかという悲痛な手紙が届いていた。
しかし、母はこれらの手紙はすべて仕組まれたものであって、ほんとうに姉や親戚から来たもの
ではないと言って、読むことすら拒否していた。父は仕方ないと思っていたが、度重なる手紙に、先方への同情と母を立ち直させるために、珍しく毅然とした態度で母を呼びつけ読むよう強く迫った。
それでも拒否した母に対して、父は母の目の前で読んで聞かせた。イチローはそばにいて、これで何かが変わるかもしれないと期待して見守っていた。父は手紙の内容を声に出した。
「……私自身はなにもいりません。でも子供たちには、もしできることなら、砂糖を少し、あるいは缶詰のお肉か水で溶いてミルクにする白い粉をお願いします。それから、すでにお願いしていることだとは重々承知ですが、もしなんとかお菓子を少し一緒にもらえたら本当にありがたいことで子供たちも喜びます。」
母は、嘘だと言い張り、その内容を受け入れようとしない。仕方なくさらに父は読み進めた。そ
れは、姉が語る日本での姉妹にとって幼い日々のエピソードだった。つまり、姉妹だからこそ知っている極めて個人的な内容であり、この手紙が明らかに姉から
来たことを示す証拠ともなる話だった。
これで母は混乱し何も言えなくなった。それを見て父は逆に不安に駆られる。しばらくして母は手紙を取り上げ自分で読んだ。そして、この手紙は姉が拷問されて書かされたものだと言い張り、そのまま寝室に姿を消してしまった。
人生を台無しにした父母
すると今度は父は、自分が母にしたことを後悔しはじめる。その軟弱なところがイチローは腹立たしかった。父は不安を紛らわそうと酒を飲む。やがて、寝室にこもってじっと動かぬままの母に言葉をかける。
「その手紙は、かあさん、なんでもないんだよ。……おまえの姉さんがそんな手紙は書くはずはないじゃないか。おまえも自分でそう言っただろう。信じちゃだめだ。さあ食べて、バカげたことは忘れなさい」
父が態度を変えたことでさらにイチローの怒りは高まり、父を激しくののしった。イチロー自身も母のことをかわいそうだとも思った。しかし、それとは別に父の態度やこの両親と自分との切っても切れない関係にいら立ちを覚える。
父は、母のことは心配するが、自分の抱える問題を理解しない、と苛立つイチローに父は言う。
「……もしお前が刑務所に行ったのが間違っていたとしても終わったことだ。すべて済んでる。でも母さんのことは、もっと深刻ではるかにむずかしいしんだよ」
そして、イチローの怒りは爆発する。
「おれは自分の人生を父さんや母さんや日本のためにめちゃくちゃにされたんだ。わかんないのか」
イチローは一刻も早く、ケンジとの約束通り一緒にポートランドへ行って、そこで新しい生活を探そうと期待する。
実現しない、母への切ない問い
アメリカの軍人として戦地に行ったケンジに対して、当然イチローの母は反感をもち、イチローに忠告する。
「あの子は日本人じゃない。私たちを相手に戦ったんだよ。父親や母親を辱しめて自分を破滅させたんだ。殺されなかったのが不運だよ」
こう言われたイチローは落胆するが、同時に心がねじ曲がってしまった母の
ことを思いむしろ哀れみの念も抱く。アメリカに来たために歪んでしまった母に同情し、できることなら母に尋ねてみたかった息子としての心の内を吐露する。
「母さん、話してくれないか、あなたは誰なんだ。日本人であることとはなんなんだ。母さんにも少女時代があったんだろう。いままでこういうことをなにも話してくれなかったよな。さあ、いまこそおれが少しでもわかるように話してくれ。暮らしてた家や母さんの父親や母親、つまりおれの祖父母のことを教えてくれ。会ったこともなければ、知りもしない。だってずいぶん昔に死んだって聞かされた以外は覚えていないよ。全部話してくれないか。ほんの少し、もう少しでいい、おじいさんおばあさんの人生と母さんの人生とそれにおれの人生が一緒になるまでのことを。きっとあるにちがいないんだから。いまなら時間があ
る、お客はいないし母さんとおれだけだ。さあ、最初から話してくれよ。母さんの髪がまっすぐで黒かったころのことを。まわりにいるみんなが日本人だったころのことを。母さんは日本で生まれたんだし、アメリカはまだ金儲けをするための海の向こうの国でも、憎い敵国でもなかったんだろう。早く、さあ早く母さん、学校で一番好きだった先生はなんていう名前なんだい」
一世と二世の親子関係の断絶を示す切ない言葉でもある。
(川井 龍介)
筆者プロフィール:
ジャーナリスト。慶應大学法学部卒。毎日新聞記者などを経て独立、ノンフィクションを中心に執筆。「大和コロニー『フロリダに日本を残した男たち』」(旬報社)、「『十九の春』を探して」、「122対0の青春」(共に講談社)などど著書多数。「No-NoBoy」の新たな翻訳を手掛ける。この夏、『ノーノー・ボーイ』の新訳を旬報社から出版予定。