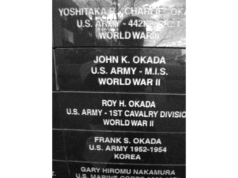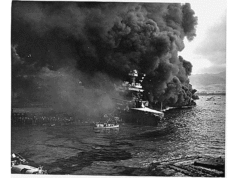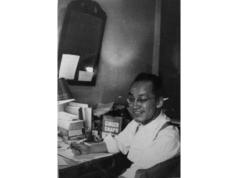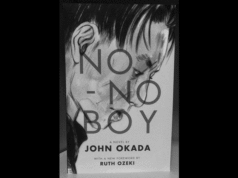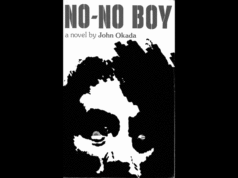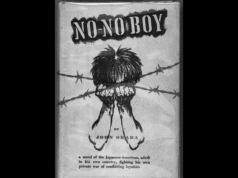太平洋戦争を挟み米国で生きた日系二世、ジョン・オカダ(JohnOkada)が残した小説「ノーノー・ボーイ(No-NoBoy)」。1971年に47歳で亡くなった彼の唯一の作品は、戦争を経験した日系人ならではの視点でアイデンティティをはじめ家族や国家・民族
と個人の在り方などさまざまなテーマを問う。いまも読み継がれるこの小説の世界を探りながらその魅力と意義を探っていく。
著者のジョン・オカダは、主人公イチローの心の葛藤を描き、同時に人間社会のさまざまな問題を読者に考えさせる。その葛藤は家族をはじめ、彼が関わっていく人間とのふれあいのなかで生まれる。
こうした人物のなかで、この章から登場する友人のケンジの存在は物語にとって非常に重く、重要になっている。
かつて学んだ大学を訪ねてみたが……
前章で、自分と同じ「ノーノー・ボーイ」の友人、フレディーに会ったイチローは、刹那的に暮らしているフレディーもまた、彼なりの闇を抱えていることを知り彼と別れる。
「いつか自分にも再び居場所ができるだろう。家を買い、家族を愛し、息子の手を取って通りを歩き、人々は立ち止まり自分たちと天気や野球や選挙について話をするだろう」
そう楽観的に考えもしたイチローは、なにげなくバスに乗り、自然とかつてエンジニアリングを学んでいた大学のキャンパスに足を運ぶ。著者はこうあらわす。
「アメリカで学生でいるということは素晴らしいことだった。アメリカでエンジニアリングを学ぶ学生でいることは美しい人生を意味した」
自由で、努力する者にはチャンスがあり、教育に応じて可能性も開ける。そういうアメリカ社会の素晴らしさを訴えると同時に、著者は、そこから取り残されそうなイチローの立場を照射する。
イチローはかつて教室に通っていたひとりの教授を訪ねてみる。だが、どうも会話はうまくいかない。日系人のイチローが戦時中どうしていたのか教授はイチローに尋ねる。
「それじゃ太平洋戦線かな。きっと捕虜の尋問にあたっていたんだね」「いや、ですから…」
自分は、軍には入らなかったこと、まして刑務所にいたことは話せなかった。大学に戻って来いという教授の助言も、「自分は人生をはく奪されてしまった」と感じているイチローには響かなかった。
なにも意味のないような会話を終えてイチローは、大学に来るべきではなかったと後悔する。
異なった問題を抱える者同士として
大学をあとにしたイチローは、偶然友人のケンジと会う。ケンジは戦地に行き、負った傷が原因で片脚を失い義足だった。つまり日系の軍人だったわけだが、エトのようにイチローを軽べつするようなところはまったくなかった。
穏やかなケンジに、イチローは自分が「ノーノー・ボーイ」であることを告白する。
傷痍軍人として、ケンジは国から新車のオールズモービルをもらっていた。でも、自慢するようなところはまったくなくこう言う。
「勲章、車、年金、それに教育もだ。ただライフルを担いだだけでだ。悪くないだろ」
片脚になり、さらにその後も傷が悪化して二度の手術で、ケンジの残った脚は11㌅になった。死の恐怖から、自殺を考えたこともあるとイチローに言う。そしてイチローの抱える問題と自分の問題を天秤に載せて量るようにイチローに質問する。
「おれが言っているのは、おれはこの先11インチがあり、おまえには50年、たぶん60年があるってことだ。おまえどっちがいい?」
イチローは答える。
「おれにはよくわからない、でもおれは11インチの方にするよ」
そう言ったもののイチローの心は揺れる。空虚な心はこの先満たされるかもしれないが、両脚がないことはずっと悲惨だと。そしてしばらくすると、思いは変わる。
「ケンジは短くても二年ほど生きられる。脚が腐るのが突然止まれば、長生きできるかもしれない。だが、この自分は、二年前には生きるのをやめてしまったのだ」
軍人になるため家を出る弟
ケンジと別れて、帰宅すると家族の間に不穏な空気が流れている。弟のタローが高校の卒業を待たずに軍に志願するといい、父親が懸命に考え直すようにタローを説得していた。
タローが志願する理由は、「ノーノー・ボーイ」であるイチローの存在であり、そして日本人であることを息子たちに求める母親であることを、タローの身になれば理解できたイチローにできることはなかった。むしろタローが出て行くことで肩の荷が下りたと感じた。
そしてタローが出て行く。父親は怯えた目をして、自分の息子が息子でなくなったように感じ、母は小さな悲鳴をあげた。家族の崩壊の兆しがこの章で示唆されている。
(敬称略)(川井龍介)
筆者プロフィール:
ジャーナリスト。慶應大学法学部卒。毎日新聞記者などを経て独立、ノンフィクションを中心に執筆。「大和コロニー『フロリダに日本を残した男たち』」(旬報社)、「『十九の春』を探して」、「122対0の青春」(共に講談社)などど著書多数。「No-NoBoy」の新たな翻訳を手掛ける。この夏、『ノーノー・ボーイ』の新訳を旬報社から出版予定。